当麻町について
当麻町を紹介
北海道上川郡当麻町(かみかわぐんとうまちょう)は、北海道の中央部に位置する自然豊かな町です。大雪山国立公園の北部にあり、美しい山々と広がる田園風景が特徴です。標高の高い地域では、四季折々の変化を楽しむことができ、春の新緑や夏の涼しさ、秋の紅葉、そして冬の雪景色が訪れる人々を魅了します。
町の中心には当麻鍾乳洞があり、長い年月をかけて形成された自然の神秘を間近に見ることができます。また、当麻町は農業が盛んで、特に米作やキュウリ、ミニトマトなどの農産物が生産されています。これらの新鮮な食材を活かした地元の料理も、訪れる人々の楽しみの一つです。
札幌や旭川からもアクセスしやすく、都会の喧騒を離れ、自然とふれあいながらリラックスできる当麻町は、観光だけでなく、アウトドアアクティビティや農業体験を楽しむことができる魅力的なエリアです。
当麻の未来像
当麻の未来像は自然・人が共存するまちであり続けること。持続可能なまちづくりは町内外からの応援により進めることができます。
交通アクセス
隣接する自治体は、旭川市、比布町、愛別町、上川町。空路を使えば、東京や大阪からも3時間程度で到着します。
地名の由来
当麻町は明治26年5月10日、永山村字トオマに、屯田兵により開拓の鍬が降ろされ、歴が始まりました。トオマの地名は、アイヌ語の「ト(沼)・オマ(に入る)・ナイ(川)」から由来しています。町内は石狩川、牛朱別川、当麻川、清水川といった河川が流れていますが、大昔は川の氾濫により、至る場所に沼や湿地があったといわれています。
位置と面積
〝北海道の屋根〟といわれる大雪山連峰の麓、東経142度50分、北緯43度82分に位置しています。北海道の穀倉地帯といわれる上川総合振興局管内のほぼ中央、東側は山伝いに上川町、愛別町、北側は大雪山系に源を発する石狩川に沿って比布町と隣り合い、南西は北・北海道の拠点都市 旭川市に接しています。面積は東西が17.3㎞、南北は13.5㎞に及び、総面積は204.90平方㎞を有しています。
気象
当麻町が属する上川地方は、盆地という地形上、独特の内陸的気候であり、寒暖の差が大きいのが特徴です。夏は30度を超える日があり、冬も厳寒期にはマイナス30度まで下がることがあります。3 月上旬頃から融雪が始まり、7 ~ 8 月頃が最も高温となりますが、8月中旬頃から次第に下降。11月に初雪、12月末には根雪となります。風向きは夏季は西風が多く、冬季には北風が多くなり、激しい吹雪の日もあります。
当麻町のビジョン
食育 木育 花育からつながる心育
命の尊さを知る「食育」
命の強さと温もりを感じる「木育」
命の優しさに触れる「花育」
大切な命から豊かな心を育てます。
当麻町のまちづくりテーマは「食育 木育 花育からつながる心育」です。
- 命の尊さを知る「食育」
- 命の強さと温もりを感じる「木育」
- 命の優しさに触れる「花育」
当麻町の豊かな自然。そこから生まれる恵みによって、我々は心豊かに暮らすことができる。それを感じ取っていただきたいという願いから3育(食育 木育 花育)によるまちづくりを掲げています。当麻町は先人が知恵と汗で築いた我が郷土を受け継ぎ、人とまちと自然が共存する、未来へ持続可能なまちづくりを進めていきます。
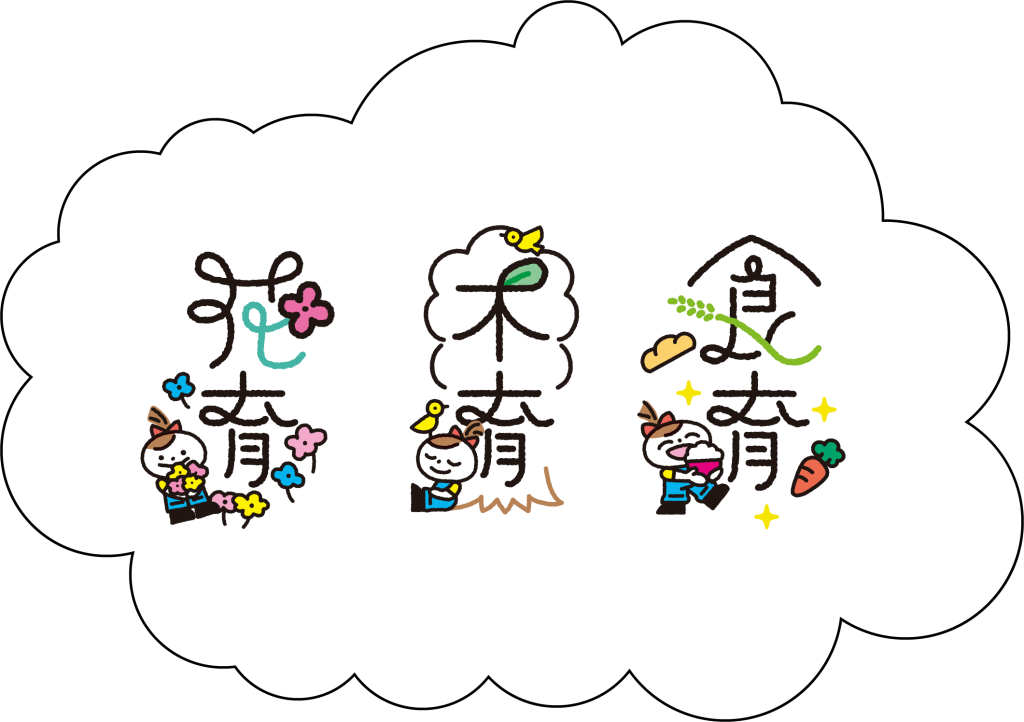
特産品

当麻米
お米を教材とした食育を進めることができるのは、当麻町が優良な〝米どころ〟だから。当麻米は全国で評価が高い北海道米の中において、トップクラスの評価を受けています。その理由は「安全安心かつ、おいしいお米」だから。
当麻町のある上川盆地の気候は、昼と夜の寒暖差が大きいという特徴があります。気温が上昇する夏場でも夜は涼しいため、病気や害虫が発生しにくいことから、農薬や化学肥料を抑えることが可能。さらに大雪山を水源として流れる水は農地に潤いを与え続けています。
今摺米は、「量より品質」という高い意識を生産者が共有し、栽培するJA当麻のブランド米。「いつでも新米の食味が味わえるお米」として消費者から定評をいただいています。その秘密は保存方法にあります。栽培したお米はカントリーエレベーターで保存しますが、この時に籾がついた状態で低温貯蔵をします。これによりお米は生命活動を維持したまま休眠。出荷直前に籾を摺ることで、摺りたて新鮮なお米を提供することができるのです。
また、カントリーエレベーターに併設された精米施設は、単一JAとして国内初の精米HACCP認証を取得。徹底した衛生管理に加え、光選別機も導入し、的確な選別も行っています。安全安心を心掛け、生産者が大切に育てたお米は出荷まで大切に管理され、皆さんの食卓へお届けします。
町内には、有機栽培米や特別栽培米などにチャレンジする生産者も。「より安全安心」、「よりおいしく」、向上心を持って取り組む生産者の背中は、子どもたちに大きな影響を与え続け、食育によるまちづくりを進める当麻町の大きな支えとなっています。

でんすけすいか
「高級すいか」として、全国に知られる当麻の特産品「でんすけすいか」。真っ黒な大玉で、シャリッとした食感と、口いっぱいに広がる果汁や甘みが特徴。JA当麻はブランド維持のために最先端の選果機を導入し、あえて厳しい基準を設定。糖度は11度、重さ4 ㎏ 、そして真円に近い形と空洞検査をクリアしたものだけが、「でんすけすいか」として市場に出されます。
でんすけすいかは、雪解けが始まる3月下旬から栽培が始まります。大きくて糖度が高く、実がぎっしりつまったすいかに育てるため、一株から一個だけを育てる「一果採り」を採用。重みによる偏りや品質の低下を防ぎ、まんべんなく日光を充てるための「玉返し」という作業を繰り返しながら、6月の初出荷を迎えます。7月下旬までという非常に短い栽培期間であり、高い栽培技術が求められます。
でんすけすいかが産声をあげたのは昭和59年。米の減反政策で日本農業が大きく変革する中、米に代わる個
性的な転作物の必要性を感じていた、当時の青年部メンバー15人が栽培を開始。当麻農業の生き残りと未来を掛けた取り組みに挑みました。名称は〝田を助ける〟という願いと、真っ黒な容姿が、喜劇俳優である故・大宮敏光さんが演じる「デン助」にそっくりだったことに由来。平成18年には、日本農業のトップランナーに贈られる日本農業賞(全国農業協同組合中央会などが主催)集団組織の部で、大賞を受賞しています。我が子のように大切に育てる生産者の姿もまた食育を進める当麻町の大切な支えです。
キュウリ
北海道でトップの生産量と販売額を誇る当麻のキュウリ。生産者が昭和54年、当麻町そ菜研究会キュウリ部会を設立。その後、品種改良や選果機更新などを重ね、着実に販売額を伸ばし、平成28年に6億円、平成30
年に7億円、現在は年間販売額8億円を記録するまでになっています。
令和元年にはJA当麻がキュウリ選別施設を導入。高性能な「長物農産物用選別装置」、「全自動箱詰めロボット」、「外観カメラ装置」により徹底した品質管理と、予冷設備による鮮度保持に務め、より高い品質を目指しています。
ミニトマト
ミニトマトも当麻が誇る農産品の一つ。6月から9月にかけて最盛期を迎えるミニトマトの品質は、市場から高い評価を得ています。JA当麻のミニトマトは、でんすけすいかと同様に糖度や大きさ、形に基準を設けています。ミニトマト選果施設には、糖度センサーや傷、大きさを見分けるカメラを設置。厳しい基準をクリアしたもののみが市場に出荷されます。
〝より良く、より安全安心に〟と、生産者とJA当麻が一体となって取り組む姿勢は、食育を学ぶ子どもたちの手本となっています。

花き栽培
花が咲く季節になると、各団体が町内の至る場所で花の植栽を始めます。町民有志のボランティア「花と緑のまちづくり推進協議会」による道の駅花壇の花植え、商工会青年部による市街地の花プランター設置、老人クラブによる花壇整備…。花育の町らしく町内は、鮮やかな花で彩られます。町花を制定しているとおり、当麻町は花の産地。多くの方が花育活動に携わっています。
バラの産地といえば温暖な地域ですが、高温多湿を嫌う特性上、夏季の出荷は全国的に減少します。当麻町はバラを夏季に栽培。これは北海道の夏が、本州と比べ湿度が低く冷涼であるため。寒暖差のある気候により生産される美しいバラは「夏バラ日本一」と呼ばれ、市場から高い評価を得ています。町花に制定されている菊は、終戦後から栽培を開始。生産者の努力と高い栽培技術は脈々と引き継がれ、北海道でも屈指の品質と生産量を誇っています。
JA当麻が出荷するバラ、菊、カーネーションなどの花は「大雪の花」というブランド名が名付けられています。開拓、戦争という厳しい時代を乗り越えて、先人がスタートさせた花の栽培。労苦を癒したであろうその優しさは今に生き、花育の根幹となっています。
先述の花植栽活動は、「花工房比呂」店長の中島大智さんが中心となり、〝美しい街並みを〟という思いのもとボランティアで行われています。花の命に癒され、心を豊かに育む花育活動は、生産者、商工業、町民皆さんの思いやりによって行うことができています。
当麻町って何があるの?
当麻町は山林に囲まれた農村地域です。いわば〝田舎町〟です。
大きなショッピングモールやアミューズメントパークはありません。しかし豊かな自然があります。自然は空気を、水を、食物を生み出し、私たちに豊かな生活を与えてくれます。
- 美味しいものがある
- 豊かな森がある
- 美しい花がある
- 人情がある
- 充実した子育て環境がある
- 整った教育環境がある
- 多世代へのサポートがある
- 元気に暮らせる環境がある
- 安全安心がある
- 文化がある
- スポーツがある
- 働く場所がある
- 移住施策がある
- 新しいチャレンジがある
つまり〝当麻町なら全部ある!〟
人として心豊かに生活できるものがそろっている町「全部ある当麻町」をキャッチフレーズにさまざまな施策を進めています。
木育活動

ふるさと思い出机
木に触れた時に感じる硬さ、柔らかさ、香り、そして樹種によって違う色合いや木目…。幼い頃から木に触れることは、お子さんが感性豊かに育つ上での一つの助力になると当麻町は捉え、木に触れる機会を積極的に設けています。
その取り組みの一つが「ふるさと思い出机」事業。当麻中学校で使用する生徒個々の学習机の材料に、町産木材を活用し、生徒自らが製作するというものです。
学校の教室にある生徒用の机は、子どもたちが毎日触れるもの。学校生活において、成長を見守り、ともに思い出を刻んでいきます。町産木材の感触を感じながら、当麻での思い出を作っていってほしいという願いを込めています。
町内の小学6年生は、中学校入学を間近に控えた2月頃、「くるみなの木遊館」に赴き、机製作を始めます。生徒たちが製作するのは、机の天板部分。町産のカバ材を使用し、「くるみなの木遊館」で加工した天板と、町内の鉄工所「世良鉄工株式会社」が製作した物入れを組み上げていきます。木工をするのは初めてという子どもがほとんど。面取りのためのやすり掛けや、ボンドによるパーツ取り付けなどに四苦八苦しながら製作していきます。完成後、机には〝自分専用の証〟として、自身の名前のプレートが取り付けられます。
春、子どもたちは真新しい制服と机とともに中学生活をスタート。さまざまな思い出を刻み、3年間を過ごします。卒業時、3年間の歩みを共に刻んだ天板には、脚が取り付けられミニテーブルとして本人にプレゼントされます。
新たな一歩を踏み出す子どもたち。心のどこかに、ふるさと当麻で過ごした思い出をしまっておいてほしいと願っています。
少年ふるさと教室
公民館事業として小学4年生を対象に開催する体験活動「少年ふるさと教室」。月に一度行われるカリキュラムの中には木育に関する体験活動も組み込まれています。
その一つが子どもたちによる森づくり。当麻山内にある人の手が入っていない山林で、子どもたちはアイデアを出し合い、森づくりを行っています。「ここはハンモックでゆっくりできる広場」、「ここは焼き肉ができる広場」など完成後のイメージを描きながら、のこぎり片手に、小さな支障木を伐りながら、人が通れる道や広場を作り出します。伐採した木は、子どもたちが機械を利用して砕き、道や広場のウッドチップとして大切に再利用。この取り組みは単年で完成するものではなく翌年、翌々年…とバトンを引き継ぎながら続きます。親となり自身の子どもを連れ、ともに遊ぶ姿を思い描きながら森を作っています。
四季折々の表情がある当麻の自然。木も季節により、それぞれの表情があります。新芽が顔をのぞかせる春、緑の葉が生い茂る夏、紅く色づいた葉がハラハラと舞い落ちる秋、真っ白な雪が覆いかぶさる冬。木の姿により、その命の感じ方は違います。当麻町では季節に応じ、趣向を変えた木育活動が行われています。
町内小中学校では授業の中で、積極的に木育活動が行われています。北海道公認の木育マイスターによる指導の下、夏は自然散策と併せて樹木の特徴などの観察、冬はスノーシューを履き、山林に住む野鳥や、葉が落ち夏と違う表情を見せる樹木の観察をしています。
木が生きる世界に入り、木に直接触れ、その命の息吹を感じる。木育活動の中で、木や自然を大切にする心を育んでほしいと願っています。
くるみなの森

人が集い、笑顔になる
笑顔が集まる森
くるみなの森
市街地からさほど離れていない場所に「当麻山」はあります。標高263メートルと非常に小さな山ですが、自然にあふれ、その環境を満喫できる施設が整備されています。私たち当麻町民にとって当麻山は幼い頃から慣れ親しんだ「里山」。この山で遊び、自然を学びました。
〝これからも当麻山にたくさんの人が訪れ、笑顔あふれる場所であってほしい〟。そんな願いを込めて、当麻山の愛称を「くるみなの森」と名付けています。クルミナはアイヌ語に由来しており、クルは「人」、ミナは「笑う」を意味します。訪れた方が笑顔になる場所であってほしいと願っています。さらに〝くるみな〟はその読み方から〝みんなが来る(来る皆)〟という意味も持っています。
多くの人でにぎわい、笑顔のあふれる場所、それが当麻山「くるみなの森」です。当麻山の麓にある木育拠点「くるみなの散歩道」と「くるみなの木遊館」、花育拠点「くるみなの庭」の名称もくるみなの森に由来したもの。町民の心のふるさとである当麻山は「食育 木育花育」の体験活動の場としても活用されています。
展望台
くるみなの森を1周する、くるみなの散歩道は当麻山の登山道にもつながっています。徒歩20分ほどの登山道は、樹木が生い茂り、さわやかな汗をかきながらの軽登山を楽しめます。秋は当麻町お勧めの紅葉スポットでもあります。
登山道の終着点には町の景観を一望できる展望台があります。四季折々の表情を見せる当麻町の街並みをぜひご覧ください。秋が深まった早朝には、雲海を望むことも可能です。冬期間は閉鎖していますが、有料でスノーシューによる登山体験も行っています。
フィールドアスレチック
くるみなの森の中にあるフィールドアスレチックでは、自然を感じながらのびのびと遊ぶことができます。30
種類のポイントは、緑の中に馴染むよう丸太やロープ、ネットなどシンプルな材料でできています。非常に簡単なものから、非常に難易度の高いものまで、さまざまなコースを用意。幅広い年齢層にお楽しみいただけるように設定しています。またポイントそれぞれに、当麻にちなんだ名称が名付けられているのも特徴です。
キャンプ場
自然の中で楽しむアウトドア。アウトドアと言えばキャンプ。くるみなの森の中にあるキャンプ場は、存分に自然を満喫しながらアウトドアも楽しめるエリアです。炊事場やトイレも設置しているので安心。バーべキューハウスでは大人数での焼き肉も可能です。また真向かいには温浴施設「ヘルシーシャトー」もあるのでお風呂の心配も無用。マットや毛布の貸し出しも行っています。冬期間は冬キャンプ場としても開放しています。
パピヨンシャトー
くるみなの森の中にある「世界の昆虫館パピヨンシャトー」では、世界中から集めた昆虫の標本1万点を展示しています。ネーミングのとおり蝶の標本は特に充実しており、中には希少価値の高い標本も…。鮮やかな色合いや特徴的な形は、自然界で生き抜くために必要なものであり、その説明も詳しく表記されています。また館内には生態観察室も備えており、生き生きと暮らす昆虫の姿を間近に観察できます。
くるみなの庭
〝美しい花や自然を五感で感じてほしい〟。そんな願いから花育の拠点「くるみなの庭」は生まれました。当麻山の麓にある〝ファミリーガーデン〟くるみなの庭には100種以上の花が咲きます。その全てが多年草植物。同じ株から毎年、花を咲かせる多年草は春に芽を出し、夏に花を咲かせ、秋には次の年に向けて休息をとります。1年をかけて変化する姿は「花が生きている」ということを教えてくれます。くるみなの庭のコンセプトは「発見・冒険・体験・創造・好奇心」。ガーデン内には、山の麓という地形をくるみなの庭生かし小高い丘や、その下を通るトンネル、背の高さまで伸びるグラス迷路、ツリーハウスなどを整備しています。かけっこ、かくれんぼ、昆虫採集…、子どもたちが自由な発想で遊べる場でもあります。さらにクライミングウォールも設置。スタッフが常駐しているので安心してボルダリングを楽しめます。
美しい花や自然の中で遊ぶことにより、豊かな感性が育つと考えます。季節を通して訪れ、花の生命に気づくことは優しさや思いやりの心が養われると考えます。大人も美しい景観の中、子どもが元気に走り回る姿に心癒されます。時には童心に返り思い切り遊ぶことも良いかもしれません。くるみなの庭は子どもも大人も笑顔になる場所です。
ここでは実をつける植物も育てています。ぜひ摘み取り、その味わいを感じてください。また多年草であるため花を摘み取ることもできます。目で花の美しさを感じ、耳で風にそよぐ花の唄を感じ、肌で花の柔らかさを感じ、口で実りの味を感じ、鼻で香りを感じる。五感をフル活用して花や自然を感じてください。
くるみなの散歩道
町民の里山である当麻山は、中心市街地にポッコリとある小さな山ですが、木が生い茂り、その下にはたくさんの動植物が暮らしています。「くるみなの散歩道」は、この当麻山を1周する約3㎞のフットパス。自然界に生きる樹木の命を感じていただくための木育拠点です。
風と鳥たちの唄を聞き、おいしい空気をいっぱいに吸い込む。森林浴を楽しみながら、木の命の力強さと優しさを感じてください。
くるみなの木遊館
くるみなの木遊館は、生活の中に使われている木を感じていただくための木育拠点です。柱や梁の構造材に町産木材を使用した木育広場には木製遊具を配置。また窓越しからは隣接された木工加工室での木材加工を覗くことができます。木工体験室では、クラフト教室なども開催しています。施設内にあふれる木の香りと触感で、樹木の命の温もりを感じてください。
豊かな森に支えられた環境

循環型林業
自然の中に生きる木、生活を豊かにする木。その命を感じる木育。木という自然の恵みを活用したまちづくりが推進できるのは、当麻町に豊富な森林資源があるから。
「豊富な森林資源を大事に」と手を付けずにそのままにしておくことは、森林の未来にとって良いことではありません。樹木は歳を重ねれば重ねるほど、二酸化炭素の吸収量が減り、さらに枯死してしまうと逆に二酸化炭素を排出してしまいます。カーボンニュートラルを目指すと同時に、未来への森づくりを進めるためには、伐期を迎えた樹木を伐り、二酸化炭素の吸収が期待できる若い木の育成が重要となります。
当麻町の民有林は約半分が人工林であり、その8割が林齢40年生を超え伐期を迎えています。その多くを管理している当麻町森林組合は、計画的に〝木を伐る→木を植える→木を育てる〟という「循環型林業」を実践し、未来へ資源を育てる林業を進めています。
そして、新たに森林組合が取り組んでいるのが、北海道立総合研究機構林業試験場が開発した新たな樹種「クリーンラーチ」の栽培。クリーンラーチとはカラマツとグイマツをかけ合わせた樹種で、野ネズミの食害に強く、成長の早さと二酸化炭素の吸収量が高いことから、地球温暖化防止の効果も期待される樹種です。
令和2年にJA当麻協力のもと、農産物の育苗ハウスにおいて、苗生産の臨床試験に成功したことから、令和6年度より事業を本格化。北海道の森林の未来を担う樹種の育成が当麻町で進められています。
森林整備は、木の成長が長期にわたるため、施策の効果がすぐ表れるものではありません。当麻町は豊かな森林の未来像を描きながら、地道に着実に森林を育てています。
木材の活用
未来へ森林資源を残す「循環型林業」を進めるためには、伐った木を有効に活用していくことも重要です。
当麻の山林から伐り出したカラマツなどの木材は、一般製材や梱包材などとして広く流通していますが、〝当麻産の木材〟と認知される機会はありません。当麻産木材の素晴らしさを広く知っていただくとともに、その価値を向上させるため、当麻町は町産木材の有効活用を進めています。その一つが住宅や店舗への町産木材活用補助。町内で新築住宅を建築し、町産木材を使用した場合、補助をしています。
公共施設にも積極的に町産木材を活用。役場は町産木材を100%使用した木造庁舎(暖房に木質バイオマスボイラーを使用)。公民館まとまーるは97%、くるみなの木遊館 、子育て総合センター、公営住宅にも積極的に町産木材を活用しています。木の香りと温もりを感じながら、利用できる空間であり、「木育と林業のまち」を具現化したシンボルでもあります。
木材をブランド化し、持続的な森林経営を支援するために、適切に管理された森林を、第三者機関が認める「森林認証制度(SGEC)」。町産木材活用の要となる当麻町森林組合は、この制度の認証事業体となっており、当麻町の民有林の多くが認証森林となっています。
当麻町の取り組みに共感し、日本郵便株式会社が令和5年、町産木材を活用した当麻郵便局を新築。役場庁舎と同様に木質バイオマスボイラーを使用し、太陽光発電も設備した局社は、環境配慮型郵便局「+(プラス)エコ郵便局」として、北海道では初めて導入された建物となっています。
当麻町の歴史と歩み
開拓の歴史
北海道の開拓と警備を目的とした屯田兵が、永山村字トオマに初めて開拓の鍬を降ろしたのは明治26年5月10日。広島、山口両県から101戸が先陣入りし、その後400戸となりました。用意された広さ16.5坪、板の間と土間の他に二間という質素な作りの屯田兵屋を母屋に家族全員で開墾にあたりました。現在の中心地(市街、中央)および北星地区から開拓がはじまり、明治27年頃からは宇園別、伊香牛地区がほぼ追給地として開拓されています。東旭川村に属していた東地区は明治38年から開拓がはじまり、大正4年に当麻へ編入されました。また緑郷、開明地区は昭和20年から戦後開拓として入植が始まりました。
村から町へ
永山村に属していたトオマは明治33年、屯田兵現役終了と同時に分離され「當麻村」となりました。漢字表記は屯田兵が麻作りを奨励しており、麻がよくとれる土地だったことから〝麻が当たる〟という意味で名付けられたといわれています。さらに昭和32年12月、北海道議会において當麻村の町制施行が決定。昭和33年4月1日に「当麻町」が誕生しました。

交通
開拓当時、隣町の愛別町との境には渡船場および駅逓があり、水陸交通の要地でした。明治22年から現在の国道39号線が起工され宇園別地区、伊香牛地区につながっています。鉄道の開通は当時の切実な願いであり、明治45年に旭川開発期成会が掲げた旭川―野上間鉄道敷設(後のJR 石北線)が當麻村を通過するか否かは、今後の発展を左右する大きな課題となりました。旭川分岐を求める東旭川村・東川村・當麻村と比布分岐を求める比布村の間の激しい争奪を経て、大正9 年に旭川分岐(新旭川駅)が決定。大正11年11月に愛別駅まで開通し、当麻には当麻駅、伊香牛駅が開業しました。
農業
開拓当初、自家用として栽培した少量の野菜、豆、蕎麦、小麦の栽培が当麻農業の起源といわれています。現在の当麻農業の主力である米は当時から栽培が行われていたという説がありますが、あくまで試験的であり量もごく少量でした。試作3年目にしてようやく約30㎏ の収穫をあげ、當麻村における水稲が有望だと認められました。明治32年には260ヘクタールを開田し、33年、42年の大規模な灌漑工事により約1130ヘクタールにおいて約277万5千㎏を収穫できるまでに至りました。凶作や2度の大戦下での不況と供出など厳しい時代を乗り越え、北海道随一の米生産地に育っています。
林業
当麻の木材は、開拓前から兵屋建設の材料として利用されていました。上川地方において、林産物として活用されるようになったのは移住者が増え始めた明治30年代からといわれています。当時の需要は角材、丸太、薪などでしたが、大正初期にかけて建築材、電柱材、枕木など、時代の発展とともに発展しました。

商工業
屯田兵入埴時、すでに本村である永山には商工業が発展していましたが、それでは足りず、荒物業を当麻に開業したことが商業の始まりとされています。明治33年の屯田兵役終了とともに土地の売買が可能となり、さらに当麻における米栽培の黎明期であったことから、徐々に開業が始まりました。大正11年の鉄道開通も発展の大きな助力となりました。

学校
屯田兵の家族には、学齢期の児童も相当数いたといわれています。これを予測し、兵屋建築とともに学校校舎の建築が進められていました。当麻における初めての学校である南北両小学校(現在の当麻小学校)が開校したのは開拓と同じ明治26年9月です。伊香牛小学校(平成17年閉校)は簡易教育所として明治34年に開校、宇園別小学校は同じく簡易教育所として明治36年、北星小学校(平成15年閉校)は当麻尋常高等小学校北分教場として明治41年、東小学校(昭和43年閉校)は東旭川村当麻教育所として明治43年、開明小学校(平成19年閉校)は当麻尋常高等小学校所属熊の沢特別簡易教授場として昭和8年、緑郷小学校(平成10年閉校)は北星小学校緑郷分校として昭和22年に開校しています。当麻中学校は当麻小学校と校舎併用する形で昭和22年に開校しています。

消防組織
明治42年、宇園別で大火があったことがきっかけとなり、有志の発起で腕用ポンプを購入し、私設消防組を組織したことが消防組織の起源となっています。その後、市街地においても、街の発展に伴い火災の危険が増したため、明治44年に有志により私設消防団が創立しました。二組の消防組は大正3年に公設消防組として認可されています。大正10年から消防団の無い地域において、それぞれ設消防団が設立されはじめ、公設となり、現在は各地区ごとに計6分団の消防団が組織されています。

郷土資料館ここから
当麻の歴史文献や資料を収蔵している「郷土資料館ここから」。この建物は初代役場庁舎として大正15年に建築されたものです。当時としては非常に珍しい鉄筋コンクリート2階建て。当時の面影をできるだけ残し令和3 年に郷土資料館としてリニューアルしました。2階には町内に現存していた屯田兵屋をそのまま移築し、当時の生活を再現している他、農機具や生活道具、文献などを展示。1階はコミュニティスペースとなっており、自由にご利用いただけます。



